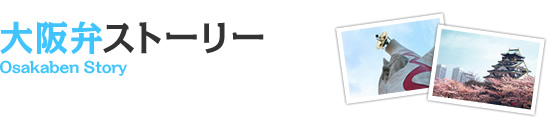上方芸能と大阪弁

ここでは標準語、共通語、方言について整理しておこう。広辞苑には、こうある。
標準語とは「一国の公用文や学校・放送などでもちいる規範としての言語」
共通語とは「いくつかの言語や方言をもつ言語社会の全域にわたって、共通に通用する言語」
方言とは「ある地方だけで使う、共通語とは異なる語」
さらに標準語と共通語の違いに触れて、こう解説されている。「標準語が規範的なのに対し、共通語は規範性はゆるい」。また、NHK「ことばのハンドブック」によれば、「NHKのアナウンサーの言葉はかつて標準語とよばれていたが、最近は共通語という言葉が使われるようになった。なぜ標準語という言葉が使われなくなったのか。一つには方言撲滅をめざした戦前の標準語普及運動の行き過ぎから、標準語という言葉に反発を感じる人が少なくないこと。また一つは標準語という名称から人々が期待するかもしれないような内容的に充実したものでは全然ないということ」とある。

ところで、大阪弁には母音が多い。「目」は「めぇ」、「歯」は「はぁ」、「手」は「てぇ」と、母音の数は二音になる。「買った」は「こうた」、「言った」は「いうた」と三音に、それぞれ一音ずつ母音が増える。「うれしくて」は「うれしゅうてなぁ〜」と長音が加わる。そのうえに「ん」が多い。「あなた」は「あんさん」になる。「ん」は、母音に次いで耳に快い音だ。母音と子音のどちらが耳に心地よいかは、育った地域の感覚で異なるが、少なくとも関西人は、「菊」より「きぃく」、「汽車」より「きぃしゃ」のほうが耳にやわらかく感じる。何より、そうしゃべるほうが楽だ。ただし、ほかの地域の人にはだらけて聞こえるらしい。これは耳の違いもあるだろう。さて、こういう「母音過多」がどういう効果を上げるか。それは、言葉に表情がつけやすいということである。「うれしゅうてなぁ〜」という言葉の表情の豊かさは、「うれしくてね」のそれより、何ほど豊かな情感を聞く人に訴えかけることか。大阪で文楽・義太夫が生まれたのも、これと無縁ではないだろう。